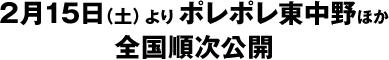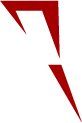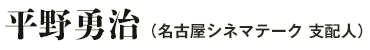
たしかに私自身、「マスメディアでは取り上げられない、そこからこぼれ落ちるような世界に光を当てた映画を上映していくのが、ミニシアターの役割」などと、折々に自らの存在証明のように言ってきた。念頭にあったのは、森達也監督の『A』。オウム真理教を扱った本作は、テレビでの放送が不可能という地点から出発したドキュメンタリーだった。そのことも、私のテレビvs映画という固定観念を培ってきた要因ではある。
それゆえに、『平成ジレンマ』『青空どろぼう』『死刑弁護人』『長良川ド根性』と次々に登場する東海テレビのドキュメンタリーを見ていくにつれ、自分の固定観念と無関心を恥じた。そして、それ以上に各作品の面白さに眼を瞠った。見るほどに、「これは、ぜひとも上映したい」と思う作品の連続だったのだ。
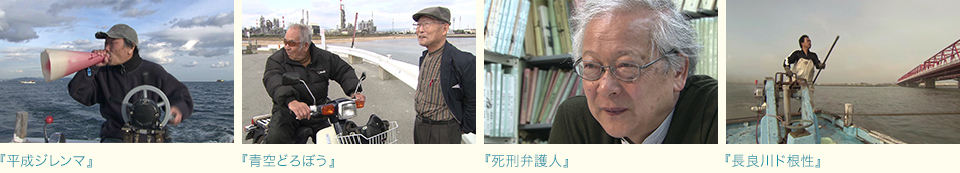
ここから次の共通点が浮上する。なぜ作り手は彼らを被写体に選んだのか。ひとつには、彼らが、自身の信じる道を生きるべく、力を尽くし、闘う人達だから。なぜ闘う必要があるのか。それは、彼らが社会のマジョリティではないからだ。彼らは、社会から浮いている。摩擦が起きている。そんな人間達を主軸に据えるとき、ドキュメンタリーは自ずと我々が属する社会の側をも描くことになる。被写体は、それ自体の魅力のみならず、社会を照らし出す鏡となり、反射を繰り返していく。この着眼点、人間と社会を見つめる視線は、凡百の映画をはるかに超えている。
かくして私は、先の自説を撤回することになった。「マスメディアでは取り上げられない、そこからこぼれ落ちるような世界に光を当てた作品」という言葉は、そのまま東海テレビのドキュメンタリーにふさわしい。しかも、それを当のマスメディアの中で堂々とやり遂げてきたのだから恐れ入る。
そうした指向は、新作『ホームレス理事長』にも確実に見てとれる。しかも、より過激な形で。本作の中心人物、NPO法人「ルーキーズ」理事長・山田豪さんのやり方は、これまでのどの主人公よりも賛否を巻き起こすだろう。チーム「ルーキーズ」の池村英樹監督の行為もまた、見る人の嫌悪を呼ぶかもしれない。しかし、彼らは、前作までの登場人物たち同様に、いや見方によってはそれ以上に自分自身の全存在を賭けて、歩き、土下座し、平手打ちを繰り出している。それに対する批判もまた全存在を賭けたものでなくては、筋が通らないだろう。そう思わせる何かが、作品には込められている。無言の気合。ドキュメンタリーの作り手も、その全存在を賭けていることは明白だ。その賭けは、テレビというメディアに、映画館という場に、我々一人ひとりに向けて、成されている。ぜひ賭けに参加してほしい。

平野勇治(ひらの ゆうじ)
1961年、名古屋市生まれ。名古屋シネマテーク支配人。
1961年、名古屋市生まれ。名古屋シネマテーク支配人。